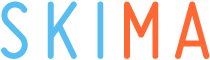跋扈ちゃん
最終ログイン:2日前ssサンプル TRPG通過後小説
宇津木弥生は不思議な夢を見た。いや、あれは夢だったのだろうか。現実と夢が地続きのようになっていた、不思議な体験。星のかけらを拾ったことで起こった出会いと別れ。星の瞬く美しくも儚い空間と、そこにいた流れ星と名乗る綺麗な女の子。
弥生には夢がある。開業医の父親に言われて医学部受験の勉強に追われてはいるが、本当は児童文学作家になりたいのだ。児童文学のやさしい世界は厳格な家族や勉強で疲れた弥生を癒してくれた。こっそりと書き溜めたアイディアノートは一番の宝物だ。
だけど、あの不思議な星空の上で、彼女は、流れ星は言ったのだ。
「あなたの言う東京?日本っていうところに行ってみたいわ。」
純粋な願いを口にして、だけど叶わないだろうという諦めにも似た表情をした流れ星に、弥生はぎゅっと胸をつかまれたような感情になった。死ぬ運命の流れ星たちは、地球に降り注いで誰かの願いを叶えるのだという。なんて儚くて、切ない話だろうか。目の前の彼女も誰かの願いを叶えて命を燃やすのだろうか。
「ねえ、最後に教えて。あなたはお願いが1つ叶うならなにをお願いする?」
その時思ったのは医学部合格でも、児童作家になることでも、どちらでもなかった。
「あなたと……流れ星さんと、東京を歩きたい、かな。」
「まあ、そんなことでいいの?」
流れ星は予想外の答えに星のように輝いている目を丸くする。
「お医者さまは?作家さんは?」
「医学部は私が頑張ればいいし、児童作家ももしかしたら何年か経ったらなれるかも。でもあなたの夢は……叶うかわからないじゃない。だから私が願った方がいいかも、って。」
流れ星はあなたって本当にお人好し、とため息をついて見せた。
これは私の、ちょっとした流れ星たちの運命への反抗だ。命を燃やして願いを叶える流れ星が、自分の夢を叶えられたらどんなに素敵なことか。
「大丈夫よ、あなたの夢は、私が必ず……。」
星の瞬く世界から、現実に引き戻される。星のかけらはサイドテーブルから消えていた。
夜空に流れ星がつう、と線を描く。彼女だ。弥生はそう直感した。
「流れ星さんの夢が、叶いますように。」
そっと、だけど強く願った。
塾の帰り道。ほくほくのたい焼きをお行儀が悪いながらも食べながら歩く。ふと、ポケットに違和感を覚えた。何かが入っているような、何か入れたかしら。
取り出してみると、それはあの子が宝物だと言っていた、出会いのきっかけになった星だった。これはあの子の宝物か、あるいはあの子自身かもしれない。ぎゅっと握りしめてみる。淡い光を放つその星は、本当にあの子が流れてきたかのように美しかった。
自室に星を持ち帰り、手のひらでころころと転がしてみる。かけらを拾ったころのような輝きはないが、確かにこれはあの星だ。淡い光はポケットやかばんに入れてしまえば見えないような明るさで、弥生は微笑んだ。
これからこの星を持ち歩こう。東京の、しょうもないところから素敵なところまで、いっぱい見せて回ろう。医学部受験の時には見守っていてもらおう。大好きよと最後に微笑んだ不思議な友達の夢が、叶ったと信じて。