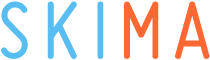小説サンプル1(セリフなし)
0
君が居なくなって、早数ヶ月。1人で過ごす夏の虚しさを思い出した。 僕の隣には誰もいない。夏なのに、冷たくて、寒い。そんな毎日が続いている。
あの日から、僕の身体は食べ物を拒み続け、最低限しか受け付けなくなった。他でもない自身の行動が僕を殺そうとしている。緩やかな自殺を繰り返しては死なずに生き残っていた。
ぼんやりとした視界の隅に、長い三つ編みが揺れる。顔を上げると、これ以上無いくらい無邪気な笑顔が、僕の目の前にあった。
「_____」
細い足がくるくると舞い、赤く彩られた唇が何かを囁く。その言葉は、窓の外から聞こえる蝉の声に、いとも簡単に掻き消されて、僕の耳には届かない。
小さな君の声は、その姿と共に、静かに消えていった。本当に小さくなって、夏空に溶け出して。きっとそうやって、誰にも認識されなっていく。いつか、僕にだって君の姿は見えなくなる。
崩れ去った儚い君との物語は、もう幻。君の面影を追いかけては、その幻影すら見えずに泣く日々の繰り返しで、意味もなく時間だけが過ぎていく。そして、僕はただ1人。この物語に自ら終止符を打つことも出来ずに、未練がましく生きている。
~~~