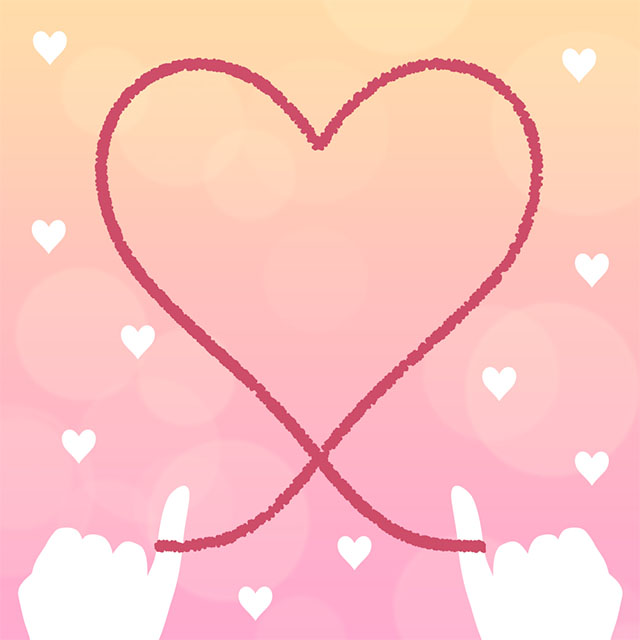【小説サンプル】少女が纏う黒い髪
私立霧崎女学園。都心から電車に揺られて二時間もした辺りの駅が最寄りで、のどかな田園風景の中に一対の白樺に門扉を覆われ、校舎を隠すような林を纏ってそこに在る。通うは良家の淑女が多く、けれど一般的な家庭の子供にも、その権利は存在していた。
(そして、今日から僕もその一員である、と……)
真っ黒な制服を纏い、僕は校門に立つ二本の大樹を見上げる。まるで自分たちが門番だ、とでも言うような、そんな厳粛さをもってそびえる白樺に何となく頭を下げ、そして学園の敷地へと足を踏み入れた。
煉瓦に覆われた道。まっすぐ前へと敷き詰められたそれを踏みながら、さわさわと軽い音を立てる木の葉に誘われるように進んでいく。今日は入学式で、本来であれば両親も参列するところではあったが、どちらもがどうしても外せない仕事があったため、(両親曰く)泣く泣く諦め僕だけを送り出すことになったのだ。
こつ、こつ。ゆったりとした足取りで歩く道。煉瓦に革靴の踵が触れては鳴き、それが原因かは判らないが胸の中心辺りに不安のような感情を抱かせる。
(受験と、合格発表の日にしか来たことがないから、きっと緊張でしょうね)
一人考えながら辿り着いた校舎。僕以外には人がおらず、勝手に入って良いものか判断がつかない。
「……」
きょろきょろと視線を彷徨わせる。誰かいないかと思っての行動は、果たして正解だったらしい。ひらりと木立の中に舞った長い髪に気付いて、僕はそちらへと足を踏み出す。できるだけ音を立てないようにと気を付けて進み、そして。
「――!」
ぶわりと強く吹いた風。唐突なそれに咄嗟に目をつむってスカートを抑え、そうして治まった風に顔を上げれば、そこには――
「あら、新入生さんかしら」
「!」
すぐ目の前、目と鼻の先にまで迫っていたその人に、僕は大きく目を見開いた。
一言で表現するならば、綺麗な人、としか言いようがなかった。真っ黒な、漆喰に似た色合いの長い髪をふわりと揺らし、優しく微笑んでいる。
「え、えっと、あの、えっ、と」
あまりにも美しいその顔にどぎまぎしている僕に、その人はこちらの内心を知っているみたいにくすくすと肩を揺らした。
「驚かせてごめんなさいね、お嬢さん。私はこの学園の中等部二年生の花宮です。貴女は?」
「あ、えっと、あの、黒子テツナ、です、一年です」
「良いお名前ね。テツナさんと呼んでも構わないかしら?」
「は、はいっ、もちろん、です!」
こくこくと頷いて了承を示せば、先輩は「ありがとう」とまた綺麗に目を細める。
「ところで、テツナさんはどうしてこんなところに? 今日は入学式よね?」
「はい、えっと、少し来るのが早すぎたみたいで、昇降口に誰もいなかったから入って良いのかが判らなくて……それで、近くに誰かいないかなと思ったら、先輩の髪が」
「髪?」
「あっ、いえ、先輩の姿が見えたので!」
「……」
髪が躍っているようだった、なんて、意味が判らないと両断されかねない。そう思っての言葉選びに、先輩はじっと僕を見下ろして。
「あんまり知らない人についていかない方が良いわ。ただでさえ私たちの制服は『特殊』なんだもの、服を剥かれるなんてことも有り得るし、そもそもテツナさんはこんなにも可愛らしいから、何かないとも限らないもの。気をつけなさいね?」
「はっ、はい……」
俯く。確かに、先輩が言っているようなことが絶対にないとは言い切れない。僕が可愛いかはともかくとして、制服の価値を知っている人は、この世にいくらでもいるのだから。
視線を伏せる僕の頭に、柔らかなぬくもりが触れる。ちらりと上目に窺えば、先輩の腕が持ち上がっていて、その先にある手が頭に乗せられているのだとはすぐに判った。
「ちゃんと反省できて、良い子ね」
「い、いえ、えっと」
「ああ、そろそろ昇降口の方に先生方がいらっしゃると思うわ。行ってらっしゃい」
何かを言いさした僕を遮り、先輩が言う。その言葉にこくこくと頷くと、彼女はひらりと踵を返した。
「それじゃあね、テツナさん。またそのうちに」
「あ、あの!」
立ち去ろうとするのを引き留め、僕は頭を勢いよく下げ。
「ありがとうございました、これからよろしくお願いします!」
そんな言葉に、先輩は小さく笑って。
「ええ、よろしくね、テツナさん」
視界の端で長い髪が揺れる。ゆっくりと顔を上げた僕の目に、薄く微笑む美しい相貌が焼き付いた瞬間だった。