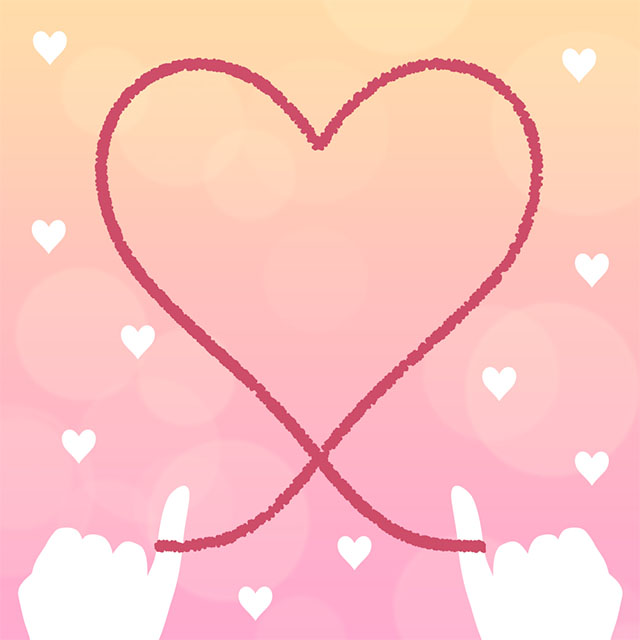【小説サンプル】私の気持ち
5
誰かを好きになることなんてなかった。親愛だって、友愛だって、――恋愛だって。どんな愛さえも、私の心を揺るがすことはなかった。
なかった、はずだった。
(なのに、なんで)
どくどくと早鐘のように脈打つ心臓。それを抑え込もうと、服の胸元を強く握る。
(信じない、私が人を好きになるだなんて、信じられる筈がない)
信じて良いわけすらない。
それなのにその人は、いとも容易く私の心を奪い去り、良いようにして。
(ふざけるな、私のオモイなんて知らないくせに)
ぎり、と唇を噛む。涙がほろりと落ちた。ぶち、と皮膚が破れる音がして、口の中に広がる鉄の味。唇を噛み千切ったと気付くには、そう時間はかからなかった。
「なぁ、なんで」
ベッドから投げ出された手。それを恐る恐る両手で握り額に寄せて、まるで祈りを捧げるようにする。
そっと目を閉じ、泣き喚きそうになるのを我慢して。
そして、私は言う。
「なんで、あんたは……私を、私のココロを、離してくれないんだ……?」
──答えは、ない。